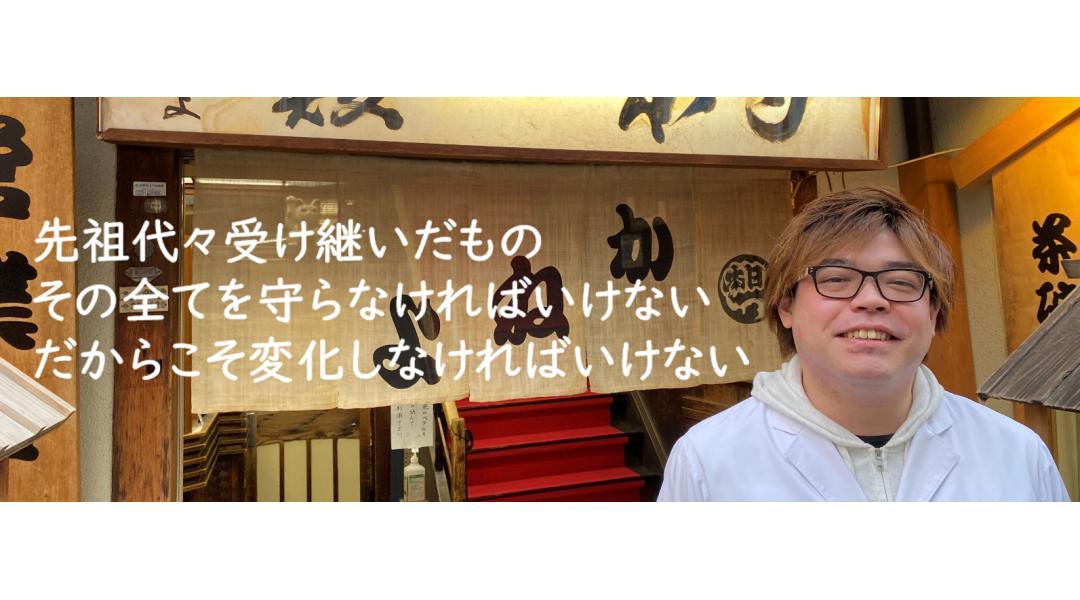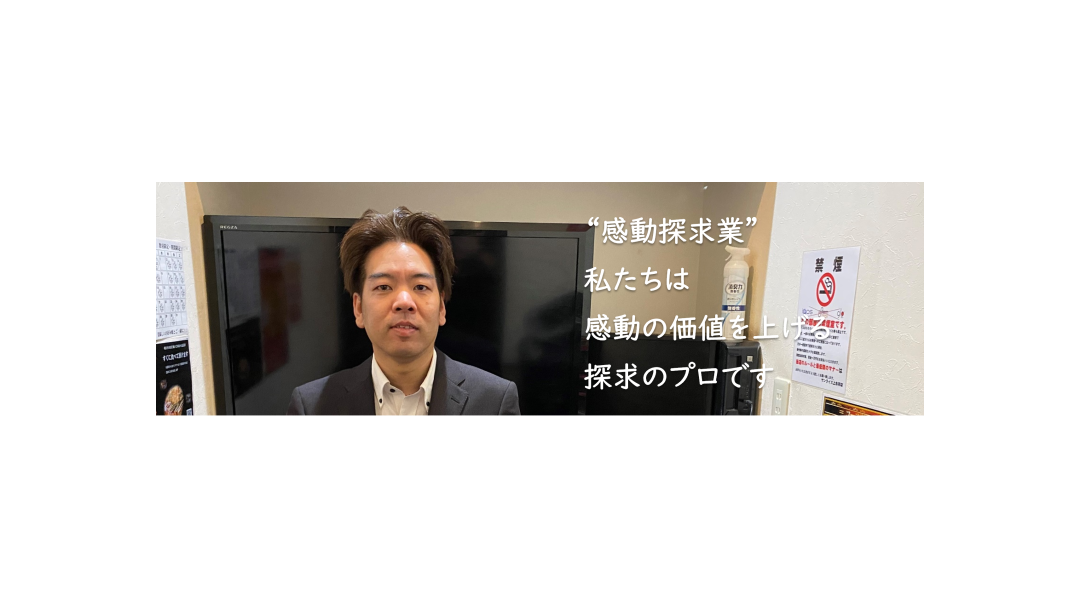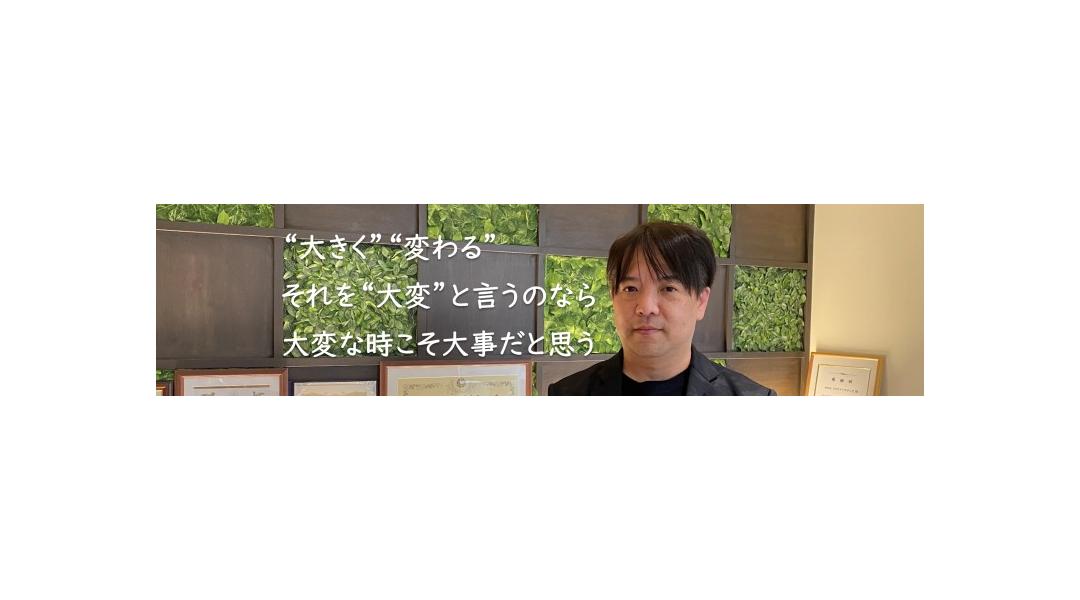経営者インタービュー詳細
VOL.30
- 投稿日:2023.5.23
- 編集日:2023.5.23
100年前から変わらないこと それを守るために"本物を作り続ける"
有限会社沙雅の人形
/
取締役大久保 佳
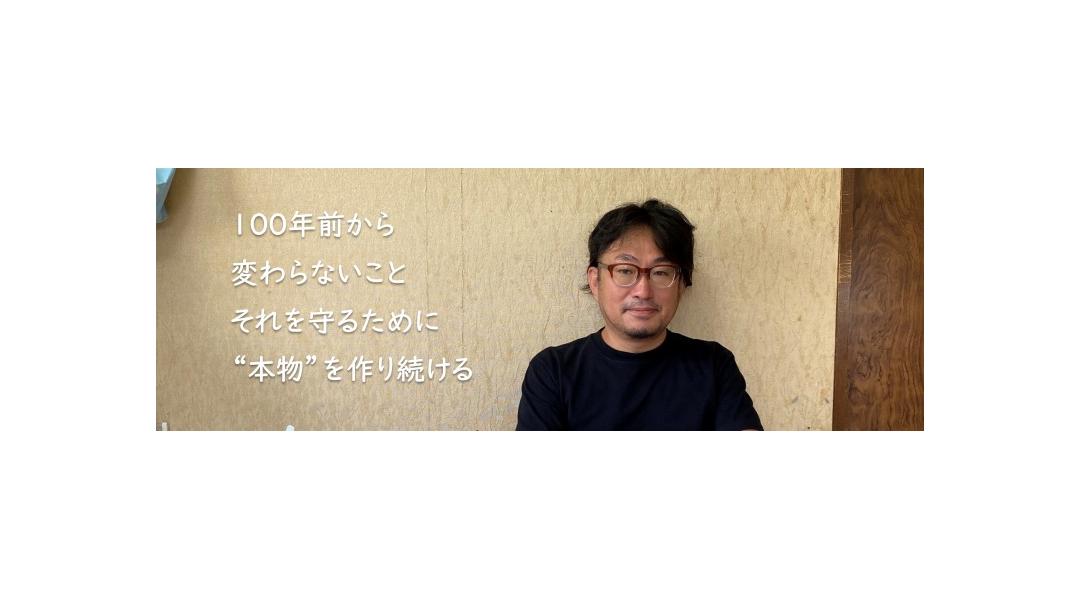
昔から、大久保家は京人形作りをやっていたんですが、昭和40年頃、私の父が本家から独立したんです。その当時、日本は高度経済成長で人形を作れば売れる。という、そんな時代でした。しかし、そんな時代も長くは続かないだろうし、京人形の需要は減っていくだろうという予測の元、雛人形づくりにシフトしたんです。しかしながら、人と同じ雛人形を作っていたのでは埋もれてしまう。何か他と違うことをしないと。と、いうことで、他の雛人形職人が使わないような素材を使いました。何を使ったかというと、人形用の生地ではなく実際人が着る着物の生地を使ったんです。この雛人形が、皆様からご評価頂き、現在の活動の原点にもなっています。
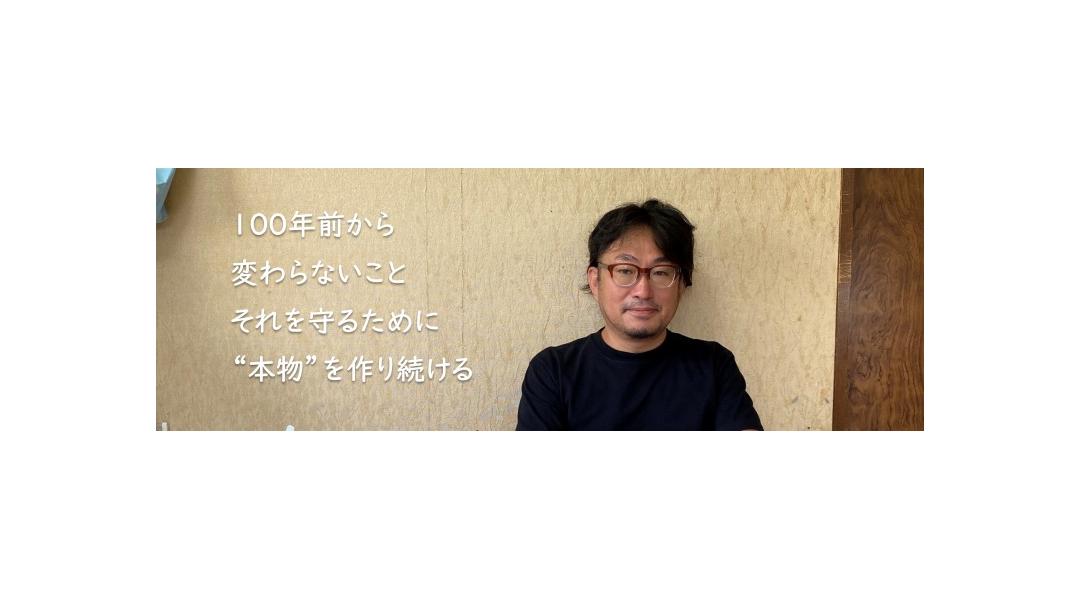
人形作りという作業は、その作業自体100年以上も昔から変わっていないんです。これは、これからも守っていかなくてはいけないと考えていますし、それを守るためには、「本物」を作り続けなくてはいけないと考えています。
バブル崩壊後の1994年。この時が、一つの転機になったように思います。バブルが崩壊したのが1993年だったのですが、いち早くその影響を受けた株や証券といった金融市場や不動産市場、そこから順番に色々な業界がバブル崩壊の影響を受けていって弊社の業界に影響が出だしたのが崩壊から約1年後の1995年でした。売上の多くの部分をい占めていた東京が完全に売れなくなったんです。その時に、「京人形のお雛様が一番」。そう思っていましたが、それにこだわりすぎると事業の存続自体が出来なくなる可能性が露呈したので、「売れる商品」を作らないといけなくなったんです。皇室に・・・とか。伊勢神宮に・・・。とか、全く通用しなくなりました。そして、この時期に、「雛人形に一枚、一枚着物を着せていく技法」を創り出したんです。それまでは、出来上がりが美しければ良い。ということが常識でした。しかし、「平安時代の人があたかも現代に蘇り、今まさに目の前に座っている。」そんなお雛様を表現するために、一枚一枚着物を着せていったんです。当時は、色々と反発とでも言いますか受け入れられない時期がありましたが、少しづつ浸透していき今に繋がっています。
人形という「モノ」を通じて、弊社で人形作りに携わってくれている職人の皆様、そして、仕入れ先をはじめとした関係先の皆様が全員笑顔で幸せにならないいけないと考えています。そして、雛人形に代表されるような文化。つまり、「コト」を世界に対して発信していかないといけないと考えいます。
コロナ禍の現在、まずは時代の流れに合わせていくことが大切なように思います。また、先程の話にも通じる部分があるのですが、今は「モノ」の時代ではないんです。何か新しい「モノ」を作ったところで、しばらくすると普通にコピーされた商品が出回ったりしたりしますから。ですから、これから創り出すべきは、「モノ」という尺度では測れないような「コト」。つまり「文化」を創り出さないといけないと考えています。その為に、私は、「お雛さん」や「節句」の文化に改めてフォーカスしています。
例えば、雛人形。皆様、ご存知の文化だとは思いますが、本来これは子供の健やかな成長を願って飾るものなんですよね。それがいつからか、雛壇の段数が多いとか少ないとか、値段が高いとか安いとか、そういうことが前に出るようになりました。段数が少なくても値段が安くても、子や孫にかける思いは一緒のはずなんですよ。「雛壇の段数」や「お金」といった「モノ」ではなく、純粋に子や孫の健やかな成長を願う思いを表現する方法として私は「はいこ」に着目しています。「はいこ」は、さるぼぼのルーツともいえる平安時代から伝わる文化で、乳幼児の病気などを身代わりに背負うとされている布製の人形です。この「はいこ」を、子や孫を思う気持ちの表現方法の新しい方法や手段として、そして、この「はいこ」や「お雛さん」「節句」の本来の意味を「文化」として、「コト」として広めたいと考えています。今、私が考える「コト」を創り出すというのは、いつからか忘れられた日本の「はいこ」の文化を現代に蘇らせることなのかもしれませんね。
ここまででもお話しましたが、「コト」を発信していくこと、創り出すことを考えています。また、弊社の雛人形を手にした皆様に後世に残したいと思って頂けるような「本物の雛人形」をこれからも作っていきます。